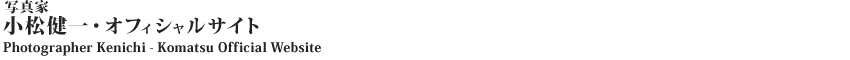3月3日、東京マラソンがおこなわれた日に、志しを同じくする四人の同世代の写真家が集った。昨年来、話し合いを続ける中で、ようやく2025年の活動の骨格が決まった。子細は後ほど伝えますが、6月に銀座の吉井画廊で4人の作品展をすること。作品集も同時刊行。各作家による作品解説や四人の対談、オープンニングパーティなども行う。来年以降も創作活動を継続するなど決めた。

4人のポートレートと集合写真を撮影してくれたのは、山岸伸さんの助手を11年にわたって務めている写真家・近井沙紀さん。山岸スタジオの中でも最ベテランだ。 ありがとう~!♡☆

撮影した写真の画像をチェックする。

師匠の山岸伸さんと近井さん。スタジオで。

鈴木さん、林さんと各自のポートレート撮影が終わって一段落。次は僕の番だ。先日行われた俳優・西田敏行さんの葬儀の遺影となった写真を撮影した同じテーブルでの撮影だと山岸さんは言った・・・。

御茶ノ水駅からの聖橋。関東大震災後の復興橋梁の一つ。1927(昭和2)年に完成している。

3月2日、故・土門拳先生の弟子をしていた現在、酒田市にある土門拳記念館の理事を務める友人の堤勝男さんの写真展に行った。兄弟子の写真家・藤森武さんと一緒に来ようと思っていたが連絡が取れなかった。

鑑賞者に作品の解説を熱心にする堤さん(中央)。背後の展作品は奈良東大寺・二月堂のお水取りの神事。

酒田の土門拳記念館で会って以来、数年ぶりの再会だった。僕が『ヒマラヤ古寺巡礼』の取材中、佛神像を撮影するにあたり、色々なアドバイスを頂いた。堤さんは師匠・土門拳の代表作『古寺巡礼』の撮影助手を藤森さんとしている。
会場で堤さんが突然「小松さんに言いたいことがある!!」と財布の中からメモを取り出した。それは以前に僕が朝日新聞に書いた「写真家の俳句」の記事の事だった。この中で土門拳の俳句を紹介した。「骨壺の子もきけ虫が鳴いている」という次女真菜ちゃんの水死事故を想って詠んだものだった。その句が正しくない、本当は「骨壺の子も耳すませ蚯蚓なく」だというのだ。直接師匠から聞いたとメモには句が記されていた。この句は土門自身が書いた「カメラ」(昭和25年12月号)にも当初の句が載っており、虫の声はコオロギの鳴声であるとも明記している。
しかし、堤さんが師匠から直接聞き、おそらく原稿も見せられたのだろう。だからこそ印象に残っていて僕が書いた記事を見てすぐに違っていると感じたに違いない。僕はそれはそれで正しいと思った。この句が思い浮かんだ時に、土門拳はあの達筆な書ですらすらと書いて近くにいた弟子の堤さんに見せたのだと思う。それが「蚯蚓なく」の句だ。堤さんの解説によるとこの鳴声は蚯蚓が面白いが、実は螻蛄なのだと師匠は言ったという。僕が思うに当初の句が「蚯蚓」、しかし土門が推敲を重ねるうちに紹介句に至ったのだと思った。俳句を詠むにあたっては当然のことである。
最初の句には「子も耳すませ」と「蚯蚓なく」という言葉があるがそれぞれ強すぎる感が否めない。推敲句の「子もきけ」の方が自然だし、実際、蚯蚓は鳴かない。季語では「秋の夜にじい~じい~と鳴く声を蚯蚓なくと言った」が実際には、それは土門が言った螻蛄の鳴声が事実である。僕は堤さんの意見を拝聴して改めて土門拳の凄さを再確認した。 鬼籍に入られて35年も経つのに師匠を心から尊敬し、誇りを持っている弟子たちがいることだ。それは藤森武さんにも強く感じることである。


一緒に行った「写真集団・上福岡」のメンバーと東京写真記者協会事務局長の清藤拡文さん(上の写真の左端)と堤勝雄さん。

写真展の鑑賞会には8人が参加した。懇親会には7人。正面は元産経新聞記者の清藤さん。後のメンバーは「写真集団・上福岡」の会員たち。右から竹川会長、一瀬事務局長。