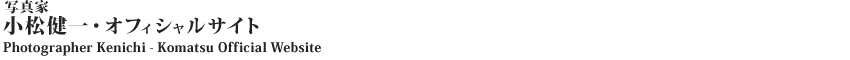今日9月11日は、あの東日本大震災と福島原発の放射能漏れ事故がおきてから、ちょうど1年半となる日だ。もう1年6ヶ月も過ぎてしまったのかという気持ちと、まだ1年半しかたっていないのか、という複雑な心境だ。しかし、現実はいまだ故郷や家に帰れず避難生活を送っている人々が三十四万人以上いるということだ。そして本格的な復旧、復興に向けての青写真はまったく描けていない。福島原発の廃炉に向けた作業にいたっては、いまだ原発内の状況の把握すらできていない。一体いま現場で何が行われているのか、国民は知る術もないのである。
こうした重要な時期に、政権政党の民主党はもとより、野党の自民党も政争に明け暮れており、被災者も国民もそっちのけで自己保身にのみ走っている。この間、国会等で決められたのは消費税の10パーセントへの値上げと電気料の大幅値上げ、それに事故が多発して多くの犠牲者を出している米軍海兵隊のオスプレイの沖縄・普天間基地への配備だけである。「世界一危険な基地」と米国さえ認めている基地にだ。僕も何度も行っているが基地の金網が校庭の境である小学校や大学、病院など街のど真ん中に基地があるのである。沖縄国際大学に米軍のヘリが墜落した時にも取材をしたが本当に一歩間違えれば大惨事になっていたのを実感したものであった・・・・・・・。
ともあれ、いまだ見つかっていない多くの行方不明の方々、犠牲になられた方々に、こころからの哀悼の意をあらためて捧げたいと思う。 合掌
写真は、この夏取材をしてきた中国・四川省と雲南省にまたがる湖、濾古湖。
9月8日、都内において、写真研究会「風」の例会が開かれた。出席者は「風」始まって以来の3人という少なさであった。しかし、人数が少ない分それだけに充実した深い内容の例会となった。森同人は一枚の花の写真を持ってきた。それは僕もはじめて見るジュン菜の花であった。この花を撮影するために3年前から準備し、今年になったからも現地の役場と連絡を取り合い、職員が実際に山間の沼まで足を運んで咲き始めたのを確認、その3日後に満を侍して出かけたという。森さんは80歳近い年齢だ。朝、4時に埼玉にある自宅を出発、自分で車を運転して往復約680キロメートル走ったそうだ。現地についても沼に入るのに長老に話、ようやく「荒らさないでくれよ・・・・・」と言われたという。荒さないでくれということは、入ってもいいということと判断してパンツなって腰まで泥沼に浸かり、三脚を立てて撮影に成功。わずか1センチにも満たないような白い可憐な花である。しかしその五つ花弁の一つ一つには無数の白い髭が生えていて何とも不思議な花であった。川で体や三脚を洗って帰路に着いたそうだが途中3度止まって車の中で休んだという。「やはり歳ですかな・・・・・」と言って笑う森さんの写真への情熱に対して鈴木事務局長とともに改めて学んだのである。
もう一人の参加者の鈴木さんは前回に続き「自分の写真史」とも言うべき作品を百十数枚持ってきた。みな四つ切に焼いたモノクロプリントである。前回は1960年代~1970年代、今回は1980年代~1990年代頃までに撮影したものだ。どの作品にもそれぞれの時代が写っており、風俗性も感じられて興味深いものであった。主に東京都内で撮影したものだった。写真展にまとめて発表するのもいいが、写真集にまとめるのが望ましいと話し合った。プリントはみな撮影した当時に自らが焼いたビンテージプリント。オリジナルプリントの価値や重要性についても話し合った。終了後、ちょうど街の祭りで青森のねぶたのパレードをしていたが、鈴木さんと2人でハネトの「ラッセイセーラッセイセー」という掛け声を窓越しに聴きながら赤ワインを傾け、3時間ほど写真創作談義をした・・・・・・・・。出席できなかった人はそれぞれのやもう得ない理由があったのだから仕方ない。
10日は、矢島保冶郎の本の編集作業に追われていたがようやく一段落着いたので、映画を観にいった。日比谷でやっていたフランス映画「最強のふたり」だ。久々の映画鑑賞だったが、「フランス人の3人に1人が笑い泣いた」といわれ、東京国際映画祭で史上初の3冠受賞という話題の映画だけあって平日の昼間なのに席はほぼ満席だった。アメリカのハリウッド映画のような派手なアクションなどはないが、淡々とした日常を描きながら、人の心の襞を丁寧に描いていて好感のもてる映画だった・・・・・・。星~☆☆☆
その後、映画を誘ってくれた友人のMさんと彼女の馴染みの店を4軒廻った。数寄屋橋で焼き鳥屋を2軒経営している女性を紹介してもらう。記念に一枚派チリ~!!